病気や障がいがあっても暮らしやすい社会に
日本では支援が確立されていないとのことですが、海外ではどのような支援が行われているのでしょうか?
林先生
例えば僕がお腹の中の赤ちゃんに対する治療を行う「胎児医療」を学んでいたイギリスでは、超音波や血液検査でお腹の中の赤ちゃんの病気や障がいを検査をすることについて、必ず情報提供があります。
受けるかどうかは妊婦さんが決めますが、7割ほどの方が検査を受けていました。超音波でもかなりの数の病気や障がいが分かるので、1時間ほどかけて検査します。
そこでもし病気や障がいがあると分かった場合、例えば唇や歯茎が生まれつき裂けている「口唇口蓋裂」であれば24時間以内にサポートチームにつなぐ、などと対応が明確に決まっています。そのサポートチームがお母さんたちを支える、という仕組みなんです。
こうした例を参考に、親子の未来を支える会の活動を進めています。
なるほど。日本とは大きく対応が違うんですね。他に、日本の課題だと感じていることはありますか?
林先生
安心して妊娠・出産・子育てするためには、病気や障がいがあったとしても暮らしやすい社会にしていく必要があると感じており、現在医療的なケアが必要な子どもの支援体制づくりも行っています。
具体的には、赤い羽根福祉基金の支援を受け、人工呼吸器をつけている子が親同伴でなくても学校に通えるような体制を構築しようとガイドラインを作成中です。
しっかりとしたサポートがあり、普通に学校に行ったり仕事もできるなら、赤ちゃんに病気や障がいがあると分かった時の気持ちや対応も変わるのではないでしょうか。
生まれる前と生まれてからを両輪で支援をしていきたいと考えています。
どんな選択をした時も、その先を支えられる社会なら心強いですよね。
林先生
産むか生まないか、検査をするかしないか、生まれてきた子どもをどう育てていくかなど、それぞれが様々な事情を抱えながら決断を下しています。
制度や支援を整えるのはもちろんですが、想像力と思いやりを持ち、それぞれの決断を尊重できる社会にしていけるといいなと思っています。
医療の進歩とともに、お腹の中にいる赤ちゃんの状態が分かる機会が増えています。 何かあった時には相談でき、支えてくれる場所があるというのはとても重要です。こうした活動が今後も広がっていってほしいと思います。
PROFILE 林伸彦先生
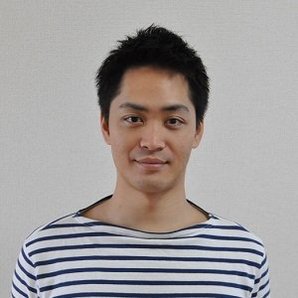
取材・文・写真/小西和香




















