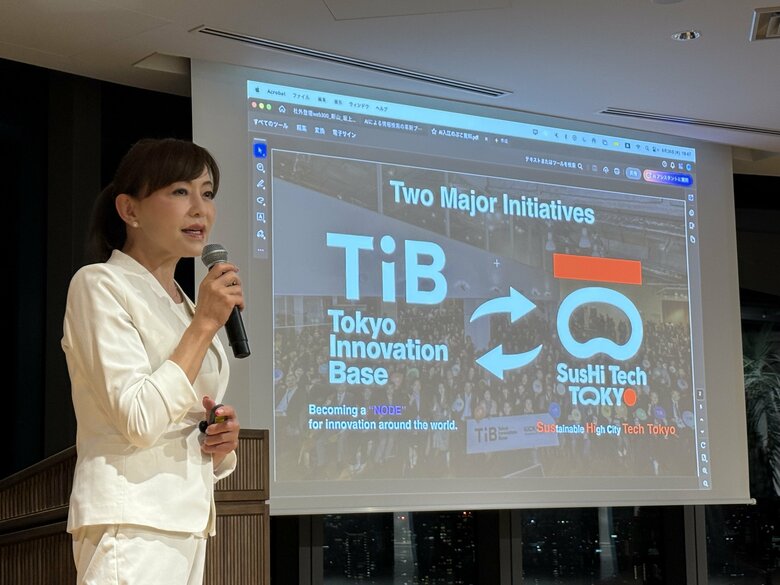最愛の夫が事故死「泣くのはひとりのときだけ」と決め
── 家族でカイロで生活するなか、1994年に旦那さんが小型飛行機墜落事故に遭われました。
入江さん:彼はいつもどおり「取材に行ってくるよ」と言って、出かけていきました。次に会ったときには、真っ黒に焼け焦げた遺体となっていて…。損傷が激しく、ススで誰かもわからないほどでした。亡くなったこともつらかったですが、最期に彼の遺体をなでることすらできなかったのが心残りでした。その後もずっと、今でも引きずっています。
── お話を聞いているだけで、おつらかっただろうと想像します。
入江さん:彼はすごく生命力にあふれる人で、周りからも愛されていました。こんなに早くいなくなるとは思ってもいませんでした。何があっても生き残れるようなバイタリティがある人だと感じていましたから。
夫が事故にあったのは、1994年12月6日。ちょうどクリスマスシーズンで、義兄が仕事でフランスに滞在していて「今年のクリスマスはみんなでパリで過ごそう」と約束していましたが、叶いませんでした。夫が亡くなった当時のことはほとんど覚えていません。1年間くらい、自分がどうやって過ごしていたのか時系列で思い出せないんです。
── それほど悲しみに暮れるなか、おひとりでお子さんたちを育てていらしたのですね。
入江さん:年が明けた春から、長男が日本の私立小学校に入学するのは決まっていたので、その前に帰国しました。4年近くカイロにいたので、自分の大学時代の友人などとは疎遠になっていたし、夫ももういない。人に話したくてもこれほど重い内容ですから、理解してもらうのは難しいだろうとあきらめていましたし、ひとりでやっていくしかないと覚悟していました。
当時、長男が6歳で、次男は11か月。時間が経つにつれ、悲しみが増していきましたが、「子どもだけはきちんと育てなければ」という気持ちだけで生きていた気がします。息子たちが成長して世に出るまで、私はリリーフ投手として頑張ろう、と強く思いました。泣くのもひとりのときだけ。息子たちの前では明るく元気な母親でいよう、と心に誓いました。
…
最愛の夫を突然、事故で亡くし、茫然自失の日々を過ごしていた入江さんでしたが、6歳と11か月になる幼子たちのために、子どもの前で泣くのはやめよう、子どもたちを立派に育てることだけ考えようと決意します。実家に戻ることもできたものの、入江さんが選んだのは古巣のフジテレビで働く道。働きぶりが認められ、契約社員から正社員となり、管理職まで務めました。新しい家族を模索した時期もありましたが、結局シングルマザーに戻った入江さん。息子たちが独立するまで、家族3人で手を携えながら幸せに暮らしたそうです。
取材・文/池守りぜね 写真提供/入江のぶこ