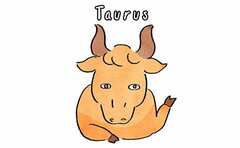「もったいない」と「幼少期の思い」が交錯して、会社に居場所を作ろうと没頭した商品作りが20年後に花開く。ドラマのような、だけど現実に、世界に類のない「米ぬかソックス」を作り出した鈴木和夫さんの年月に迫ります。(全2回中の1回)
会社で居場所がない「米ぬかソックスの商品化」に意気込む
── 米ぬかの成分を配合した画期的なアイデアで話題の靴下「歩くぬか袋」。開発者は、奈良県に66年続く鈴木靴下の2代目・鈴木和夫さん。米ぬかを靴下に使おうと考えたきっかけを教えてください。

鈴木さん:うちはもともと兼業農家で、鈴木靴下は父がおこした会社でした。私は大学生のときから靴下工場を手伝い、同時にいまも田んぼで耕作をしています。米を精米すると米ぬかがたくさん出るけれど、いつも破棄していて「もったいないな、これを何かに活用できないか」という気持ちがずっとありました。
あるとき、小学生のころに米ぬかの入った袋で廊下を拭くと、ピカピカに黒光りしていたのを思い出して。米ぬかで靴下を作ったら足がスベスベになるのでは、と思いついたんです。ただ、糸を扱う商社の方に「米ぬかを糸にできないか」と持ちかけても、相手にしてもらえなくて。私が25歳のときでした。そこから手作りで開発を始めるまで20年のブランクがあり、完成はさらに3年かかりました。

── 発案から20年を費やした?
鈴木さん:20年温め続けていた感じです。私自身、鈴木靴下の2代目として入社はしたものの、自分の居場所がなくて。みんなは新製品の企画など仕事をどんどん任せてもらっているのに、私はいつまでも糸の片づけや仕わけといった地道な作業が多く、2代目としてやりがいのある仕事を見つけたいと悶々としていました。米ぬかに対しての思いも忘れられずにいましたので、「じゃあ、1回、実際に手作りでやってみよう」と考えたんです。
米ぬかは古くから美容アイテムとして愛用され、江戸時代には洗浄料としても使われてきました。子どもが砂場で遊ぶと砂が靴下の編み目に入ってなかなか取れなくなることを連想し、鍋に靴下と米ぬかを入れて、グツグツ煮込むことで靴下に米ぬかが付着するのでは?と仮説を立てました。