
『SAKURA』『YELL/じょいふる』『ありがとう』など数多くのヒット曲を披露し、その多くの楽曲で作詞・作曲を担ってきた水野良樹さん。
デビュー以来、性別や年代を問わず、誰からも愛される作品を生み続けてきたその背景には、どのような秘話があったのか。水野さんの仕事観や、成功へのマインドについて聞きました。
女性ボーカルじゃ僕の想いは託せない
── いきものがかりといえば、誰もが口ずさみたくなるポップな作風という印象を持つ人が多いと思いますが、活動当初から現在のような好感度の高い楽曲を作られていたんでしょうか。
水野さん:
いえいえ、音楽に夢中になり始めた10代の頃は、他人と自分がどれだけ違うかを主張したいという、いわゆる思春期らしい思いを持っていました。
学校生活が充実しているタイプではなく友達も少ない内向的な性格で、世の中に対して鬱積したものがあるような生徒だったから、当時の僕が、いわゆるポップスをやっている今の僕を見たら「何してんの?」と思うんじゃないですかね。
当時は路上ライブというものが流行っていたので、(メンバーの)山下(穂尊さん)と「ゆず」を真似して女子高の近くでやったらモテるんじゃないかという極めて高校生らしい動機でバンド活動を始めてみました。
そこに、女子メンバーの吉岡(聖恵さん)が入って、いきものがかりがスタートしたんですが、最初は葛藤があったんですよ。
まず、ボーカルが女の子である以上、僕自身の想いを歌うことは出来ないという当たり前のことに気付く。しかも、吉岡は僕とは全然違う社交的なキャラクターですから、このグループに自分の人生を賭けることは出来ないなって。そう思ったのが19~20歳の頃でした。
── そこから、自分の気持ちとどのように折り合いをつけていったんでしょう。

水野さん:
事務所に入りたての頃、偉い大人たちから「女の子ボーカルなんだから、女の子が好きそうな恋愛の曲を書け」と言われたり。そんな事務的な指示をされても、どんな言葉を書けばいいのか僕にはわからなくて、完全に試行錯誤…。それでも「えいや!」という思いで『コイスルオトメ』という曲を書いたら、女子高生のリスナーたちから「なんで私の心がわかるんですか」とか、「彼氏のことを思い出しました」とか、たくさん言われたんです。
女の子にとっての初めての恋なんて、とても大切な出来事で、下手したら親友にすら打ち明けてないかもしれないじゃないですか。そんなパーソナルなことを見ず知らずのお兄ちゃんに話すって、すごいなと思ったんです。
自尊心よりも誰かの役に立つことに価値がある
── 「自分のやりたいこととは関係ない」とは思わなかった。
水野さん:
思わなかったですね。自分自身をうまく表現できて、そのことを褒めてもらうとか、そんなプライドよりも、僕の曲を聴いた人が感動してくれる。そのことが単純に嬉しかったし、そっちのほうが価値あることなんじゃないかと思いました。まあ、今は大人だから「自分の中で完結してしまう喜びなんてつまんないよね」と言えるのかもしれないですけどね。

── 20歳頃にそう思えるのはすごいです。
水野さん:
「俺が俺が!」という時期ですからね(笑)。
でも、いきものがかりは男女分かれたグループであることで、性別に縛られない曲を書ける。それってすごく面白い場所だなと考え方が変わったんです。そこから、曲作りに広がりも出ました。
26歳のときに書いた『YELL』は中学校の卒業式で歌われるようになったんですけど、当時も、自分よりひとまわりも年下の中学生の気持ちなんかわからないと思いましたよ。
だけど、わからないなりにもその世代の人たちと気持ちが繋がれたということが嬉しくて。そんな風にポップスを作っていきたいと、20代後半には心から思うようになった気がします。
当事者であることからは逃げられない
── お話を伺っていて、物事をとても俯瞰的に捉えてらっしゃる印象を受けます。そういう思考習慣は昔から?
水野さん:
(大学で)社会学部に進学したのは大きかった気がします。
入学当初は大きな動機もなく、広く浅く学べるかなという程度の認識だったんですが、最初の概論のような授業で、先生が「社会学というのは世の中を俯瞰的に見る学問なので、あたかもすべてを分析できると思いがちだけど、自分も常に世の中の影響を受け得る当事者であることから逃れられない。そのことを忘れるな」と言われたのがとてもインパクトがあって。
この視点はその後の人生にプラスになったと思いますね。
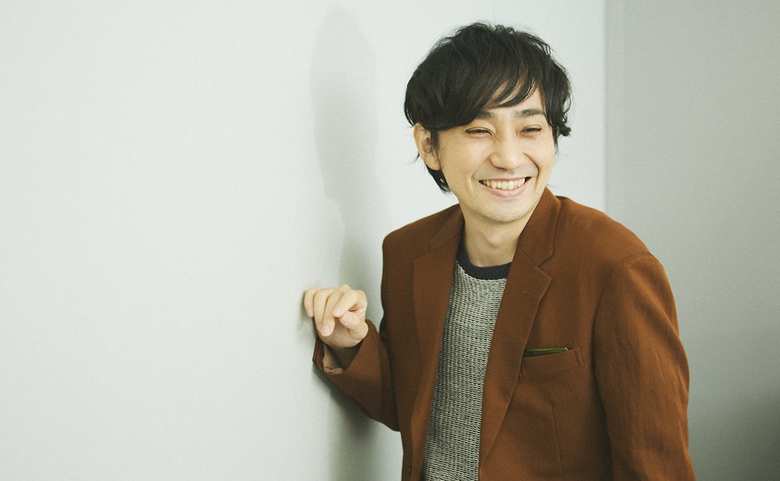
音楽業界は、運にも左右される厳しい競争社会ですから、自分たちをシビアに見ざるを得ないんですよ。例えばデビュー前に複数のアーティストが集められたライブハウスで業界人相手にお披露目ライブみたいなものをやったときも、他の人はいろんな関係者から声がかかるのに、僕らだけ「頑張ってね」のひと言でまったく相手にされなかったり。
そんな経験を積む中で、自分たちの価値は何なのか、僕らのやりたいことを100%表現するのは無理だとしても、その確率を99%にするにはどうすればいいんだろう、どうやったら生き残れるんだろうと、客観的に考えるしかなかったんです。
── 考え抜いて辿り着いたのが、誰からも愛される普遍的なポップスだったというのが興味深いです。
水野さん:
僕らがデビューした頃は、その席が意外と空いていたんですよ。90年代の後半頃はCDバブルで、個性の塊みたいな人が大勢いたんですが、ライブハウスに出ていくと、どれだけ自分が他の人とは違うかということを主張する人ばかりで、その行為自体が普通過ぎて全然目立たない。だから、「みんなに聴いて欲しいんです」というスタイルは逆に目立った。
そもそも自分たち自身、尖った音楽よりも、J-POPと言われるような、お茶の間から流れてくる音楽に育ててもらったという意識が強かったから、もし僕らが成功するためには、逆にそこしかないと思ったんです。
PROFILE 水野良樹さん

文/井上佳子 写真/坂脇卓也






















