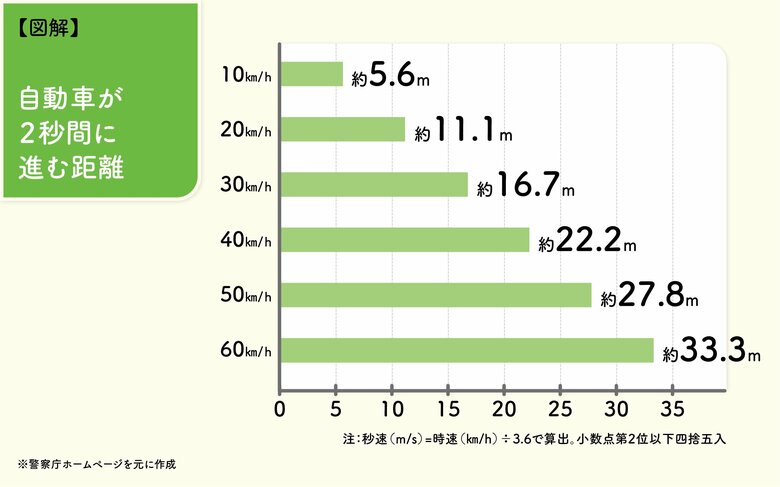バス運転手が出勤前の“蒸しパン”を食べたことで、アルコールが検知され懲戒処分になったニュースが10月末に流れました。ながら運転や飲酒運転、「自分は大丈夫」と思っている人こそ要注意。事故を起こさないよう知っておきたい境界線を、鬼沢健士弁護士に聞きました。
ながら運転「ハンズフリー通話」はどうなるの?
── ながら運転といえば、車を運転しながらのスマホの使用がまず浮かびます。「ながら運転禁止」に関して、法律はどのように規定しているのでしょうか?
鬼沢さん:
道路交通法第71条5項の5、運転者の遵守事項として記されています。
車が停止しているときを除く前提で、「携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(全部または一部を手で保持しなければ送信及び受信ができないものに限る)を通話のために使用し、または持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」としています。
要するに、「運転中にスマホを持って通話する」「運転中にスマホの画面を注視する」行為を禁じています。安全運転に支障をきたし、事故の危険を伴うからです。

──「スマホを持って通話」がNGなら、ハンズフリー通話はどうなりますか?
鬼沢さん:
スマホを車内のホルダーに固定し、画面も注視することなく運転していれば、ながら運転にはあたりません。
手の保持や視線を移す行為は避けられるため、安全運転が確保されている状態といえます。
ハンズフリー通話には耳にイヤホンを装着し、相手と会話する方法もありますが、こちらはセーフとは言いきれません。
国の道路交通法にはイヤホンの使用を違反とする厳密な規定はないですが、都道府県の一部では条例で禁止しているからです。
たとえば神奈川県では、「大音量で、またはイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車または自転車を運転しないこと」(神奈川県道路交通法施行細則第11条第5号)としています。
つまりイヤホンの使用により、クラクションや警察官の指示など「安全な運転に必要な音また声が聞こえない状態」を招くため、条例で規制しているわけです。
運転中のスマホ使用で1万円以上の反則金に…
── では、信号待ちのときのスマホ使用は?
鬼沢さん:
信号待ちは車が「停止状態」です。法律で「車の停止中を除く」としているため、赤信号で止まっているときの通話や画面注視はながら運転にあたりません。
渋滞中などのろのろ走っているときは、ついスマホに手を伸ばしてしまう人もいるのではないでしょうか。
クリープ現象で少しでも車が動けば停止状態でなくなり、その間、スマホを使用していたら違反となります。安全のためにも使用は避けましょう。
── 違反した場合の罰則は?
鬼沢さん:
運転中にスマホを保持して通話または画面を注視した場合、違反点数は3点、反則金1万8000円(普通車の場合)となります。
スマホの使用で交通事故を起こした場合には、もっと重い処分が下されます。
「奈良漬け」でアルコールが検出されることも
── 同様に事故につながりやすい「飲酒運転」は法律違反で厳罰ですが、“無意識”に飲酒運転しているケースもあるようですね。
鬼沢さん:
よく問題視されるのが「酒気残り」運転。前夜に深酒し、アルコールが体から抜けきらない状態での運転で、これは当然アウトです。
アルコールの分解速度は個人差がありますが、たとえばビール500mlを飲んだ場合、アルコールが体から完全に抜け切るまで男性で約4時間、女性で約5時間かかると言われています。
「お酒は強いほうだから」と過信せず、深酒した翌日はとくに体から完全に抜けきるまで運転は控えましょう。
注意すべきはお酒だけに限りません。アルコールは“食べ物や栄養ドリンク”にも含まれています。
お酒の弱い人であれば、それらの摂取が飲酒運転につながることも想定されますね。
── どんな食べ物が危険なのでしょうか?
鬼沢さん:
洋酒入りのチョコレート(ウィスキーボンボンなど)、奈良漬け、酒粕、発酵食品などが挙げられます。
今年10月末、大阪の市営バス運転手が乗務前のアルコール検査で引っかかり、その原因が出勤途中に食べた“蒸しパン”だったと報道されました。
蒸しパンは発酵食品のひとつ。アルコールを含むとはいえ、驚きでしたね。
── 運転中は、スマホを持たない、見ないを徹底すること。一方、安全のためにもアルコールを含む食べ物や飲料も注意したいものです。
PROFILE 鬼沢健士さん
2009年、慶應義塾大学大学院法務研究科修了。10年、司法試験合格。12年、茨城県弁護士会に登録し、取手市に「じょうばん法律事務所」を開設。交通事故、労働問題(被用者側)、インターネット詐欺を中心に取り扱う。
取材・文/百瀬康司 図版/アイル企画 参考/特定非営利活動法人ASKホームページ