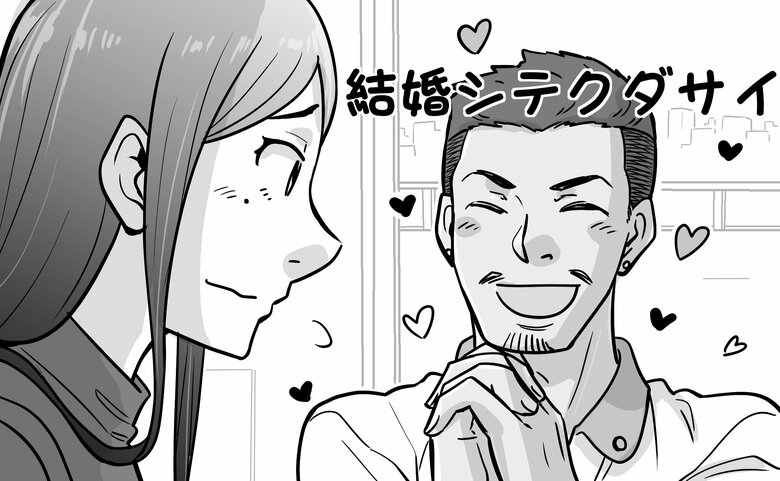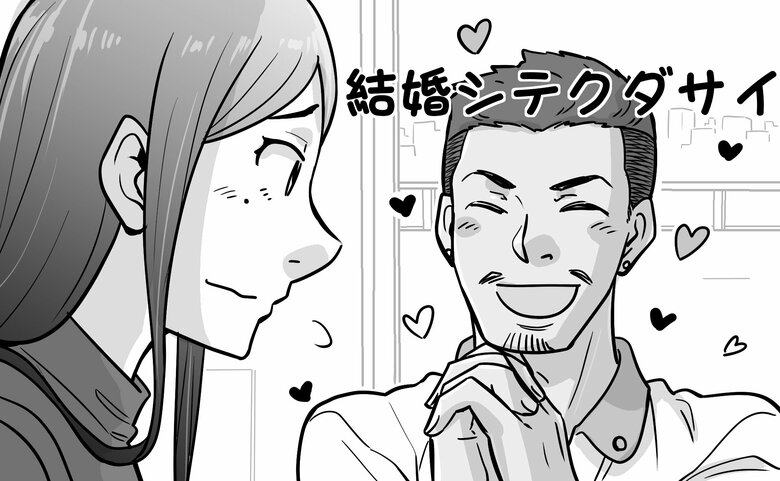夫の地元で暮らし始めると…「すべてが違う!」
ところが彼の地元での大家族との暮らしは、想像以上につらかったと彼女は言います。
「日本から大学を卒業した嫁がやってきた、と地元ではけっこう騒ぎになりました」
しかも彼は、父親が会社経営者だと言っていたそうですが、そんな実態もない。
「いろんな人が出入りしていて、誰が家族で誰が他人かもよくわからない。私は朝からご飯を作らされ、膨大な量の洗濯物をさせられ…。
“ふたりきりで暮らしたい”と言ったら、“僕は長男だから家を捨てられない”と言われて」
何かが違う、いや、すべてが違うと彼女は思うようになっていきました。そして2年後、娘が産まれると、義母が「女の子じゃ役に立たない」と言っていると夫に聞かされ、彼女の中で何かがキレたそうです。
「でも、生まれて間もない赤ちゃんを飛行機に乗せるのが怖かった。だから生後半年になるのを待って、娘とふたり、日本に帰国しました。
夫には“子どもを親に見せるね”と言って出てきましたが、もう戻るつもりはありません」
じつは夫の親戚からはたかられて、多くの電化製品を買わされ、貯金が底をつくのも怖かった、とマリナさんはいいます。
「誰かに何かを言われても、夫はいっさい私をかばってくれなかったのにも心が折れました」
その後、彼は追いかけてきて彼女の実家で暮らし始めたものの、日本での環境がつらかったのでしょう。もうムリだと帰ってしまったそうです。
「電球を食べることが愛情表現だとする彼が、当時は“情熱的”に思えたけど、彼はただ、釣った魚に餌はやらないタイプだったんですよね。私ももう少し、じっくりつきあってみればよかったんだけど…」
現在、彼女は仕事をしながら、実家の両親と娘と4人暮らし。穏やかな日常を満喫しているそう。
愛情は形にはできないもの。それをわかっていながら、可視化できるものを信じてしまう気持ちも理解できます。情熱にほだされたら、一歩引いて考える時間も必要なのかもしれません。
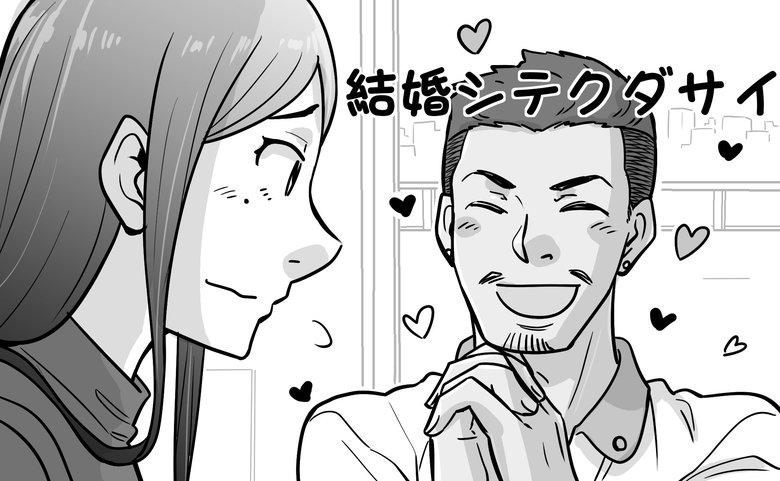

文/亀山早苗 イラスト/前山三都里
※この連載はライターの亀山早苗さんがこれまで4000件に及ぶ取材を通じて知った、夫婦や家族などの事情やエピソードを元に執筆しています。