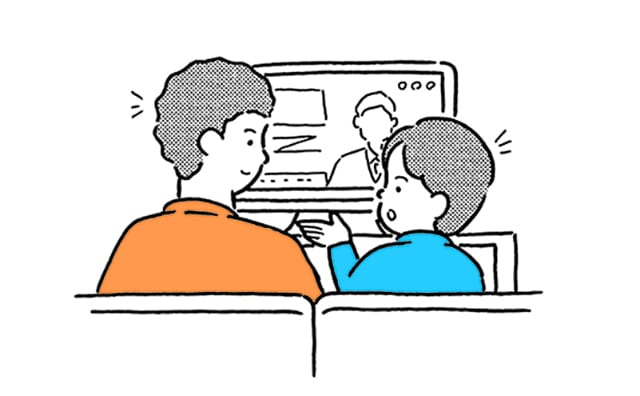新学習指導要領が「主体的・対話的で深い学び」を提示するなど、今、子どもたちには「主体的に学び、考える力」が求められています。
教育研究者の山崎聡一郎さんは、「法教育は、主体的に考える“法的思考力”を養うもの。まずは日々のニュースを教材にして、家庭で話し合うことから始めてほしい」と話します。
法的思考力で人生の課題が見つかる
── 法教育は「法的思考力」を養うものと伺いました。法的思考力とは具体的にどういった思考力でしょうか。
山崎さん:
問題を発見し、さまざまな判断材料の中から、妥当な結論を導き出す力です。
実は法教育の目標は、「法律を批判できる子どもを育てること」でもあります。
逆説的になりますが、法律を批判できる子どもは法律を守ります。それは「今の法律ってどうなの?」という発想で法律と向き合うことで、法律の中身、成立の背景、社会的な意義を理解しようとするから。そこでその法律に納得すれば、守るようになるんです。
法律と向き合うことで、社会の課題に気づき、解決策を探る力が身につきます。法的思考力は、人生の課題を見つけるうえでも役立つでしょう。
── 多くの保護者にとって「法教育」は未知の学問です。どう関わればいいでしょうか。
山崎さん:
「決定を押しつけない」が大前提ですね。
法教育と聞くと、子どもに社会のルールを教えるものというイメージを持ちがちです。法律を校則と同じように捉えて「ルールなんだから守りなさい。覚えなさい」と押しつけてしまうんですね。
そうすると子どもは言われたとおりにしておけばいいやと思ってしまい、法律と向き合わない。結果として、主体的に考える力や法的思考力は養われません。
法的思考力は「この法律はなぜあるのか」「Aさんにとってはいい法律だけど、Bさんにとっては不利益ではないか」などたくさんの意見を知ることで深まるもの。
保護者のみなさんは、法律を教えなくていいんです。子どもと一緒に法律と向き合い、意見を交換することで、法的思考力を伸ばしてあげてほしいと思います。
子どもと日々のニュースについて話そう
── 子どもが法律に興味を持ったり、考えたりするきっかけって何でしょう。難しそうですね。
山崎さん:
日々のニュースには法律問題が必ず出てくるので、そこをフックに会話をするのがいいと思います。
例えば、「有名人が薬物で逮捕された。でも、執行猶予で生活できている」みたいなニュース。子どもの感覚だと、逮捕されたのになんで牢屋に入らないの?と思いますよね。こういうときの「なぜ?どうして?」をきっかけに、インターネットや図書館で一緒に調べてみてください。
── その際のポイントはありますか?
山崎さん:
「知ったかぶりをしない」「結論を無理に出さない」ことです。
「この問題はあの人が悪い」「みっともない」「かわいそう」などと結論ありきで話してしまうと、保護者が持っている偏りが子どもに移ってしまいます。
ウクライナ情勢に関しても、知ったかぶりや結論ありきで話すのではなく「わからないから一緒に調べよう」という姿勢が大事なんです。そして、調べた後も無理に結論を出そうとしないこと。結論というのも、時代や状況によって流動的だということを覚えておくといいですね。
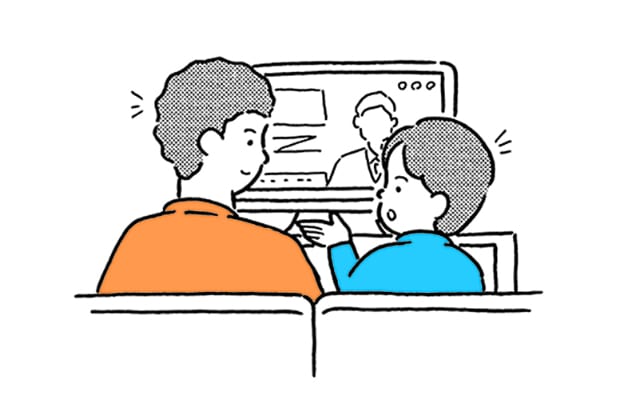
── ネットトラブルなど、身近な事例をフックに話すのはどうでしょうか。
山崎さん:
いいですね。
総務省ではネットトラブルの事例集パンフレットを出していますし、そうしたテーマを扱った書籍も多くあります。そういったもののなかから使いやすいものをひとつ家庭に用意し、子どもの手の届くところに置いておくのがおすすめです。
子ども自身が調べられる環境を整えておく
── 山崎さん自身は、中学生のときにみずから法律を学ぶようになったそうですね。
山崎さん:
はい、そうです。親から強制されたわけでもなく、それこそ主体的な学びでした。
僕自身、法律についての興味は小学生の頃からありました。ただ、通っていた小学校の図書室には法律の本がなかった。中学校で初めて法律書に出会って調べるようになりましたね。
── 図書室で本を調べるという習慣はあったのですね。
山崎さん:
インターネットもそれほど発達していませんでしたからね。わからないことは図書館で調べていました。
子どもが主体的に何かを知りたいと思ったとき、自分で調べられる環境を整えておくことはとても大事だと思います。
そもそも僕が出版した『こども六法』シリーズも、子どもの手の届くところに法律の知識を置いておきたい、図鑑や辞書と同じように置いてほしいという狙いがありますから。
実際に読むか読まないかは別にして、いろいろな知識にアクセスできる環境と方法を子どもに開いておく。そして、わからないことがあれば、保護者も一緒になって本を開き調べ、考える習慣を身につけておく。その積み重ねが、主体的に考える力を養います。
PROFILE 山崎聡一郎さん

取材・文/服部椿 イラスト/加納徳博