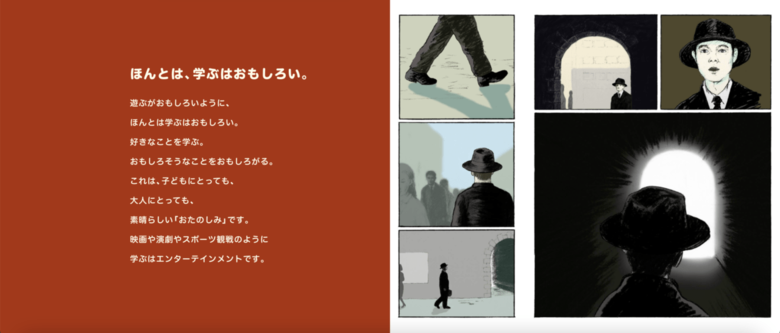ユニークな工夫満載のロングセラー「ほぼ日手帳」で知られる株式会社ほぼ日が6月、スマートフォンのアプリで学べる「ほぼ日の學校」をスタートしました。10月にはPCやタブレットでも見られるWeb版をリリースしています。
授業ではクリエーター、スポーツ選手、学者から占い師まで、個性豊かな「先生」が、自らの人生経験や専門分野について語っています。
なぜ、ほぼ日は「学校」をつくろうと思ったのか。いま必要な「学び」とは?ほぼ日を率いるコピーライターの糸井重里さんにお話をうかがいました。
僕がいなくなっても学びの面白さをお知らせしたい
── なぜ、いま「学校」をつくろうと思ったのですか?
糸井さん:
人って、誰かの話を聞いたり、学んだりすることが大好きだって思うんです。展覧会に行ったって、みんな(展示説明の)字を読んでるじゃないですか。
これってもう欲望ですよ。学ぶって、本当はものすごく面白いことで、映画やスポーツ観戦のような、またはディズニーランドのようなエンターテインメントだと思います。


学びは、人に会うことから始まり、その人の経験や、感動や知恵や失敗を聞くことです。
日常生活では聞けない色んな話を聞く機会を、人は求めている。
それは、話し手が持っている空気感かもしれないし、「あれ、おもしろいよね」という共感かもしれない。人が本気で、真剣に話す場面って、なかなか出会わないですよね。
ほぼ日の仕事をやっていると忙しいし、同じことを繰り返しても回っていくんです。でもそれは、僕にとっては退屈なことで「このままじゃだめだな」というのはずっと思っていました。
僕が魅力を感じたものをコンテンツにしていくのだとして、20年も30年も同じ物をみんなにお知らせしているとしたら、それって、なんだかものすごくさぼっているな、と。
時代と一緒に息をして動いていかないと、ひとりの人が作るものは老いていく。それはつまらないわけです。

だから、一緒に時代を生きている人間として、僕自身も新しくなりながら、みんなにこんな面白いことがあったんだよ、とお知らせすることを“死なない回転”でやっていきたいと思いました。
僕がいなくなってからもそれができるような。それで準備できたのがいまだった。
ほぼ日の學校が目指す「生々しい学び」の正体
── いま、どのような学びが求められていると思いますか?
糸井さん:
(先生は授業で、自らの体験という)手の内を出してますから、ほぼ日の學校の授業って、オンラインだけど、僕が驚くほど生々しいんです。
やり始めてからわかったんだけど、その人が持っているコンテンツが生々しければ届きます。編集者が人を集めて、「人が引き付けられる文章教室」とかやってもダメなわけで。大事なのは「生々しさ」なんです。
── 生々しさ?
糸井さん:
たとえば、(演歌歌手の)前川清さんは、いつも本音に近いところはしゃべってるけど、本音は絶対しゃべらなかった人です。
(テレビ番組で)旅をしておばあちゃんの話を聞いて、おばあちゃんの本音も引き出すし、切実に「そうですね」って言っている前川さんは、本当にそう思っておばあちゃんの話を聞いてる。でも、前川さんはみずからについては本当のことなんか言いやしない。
その前川さんが、ほぼ日の授業では、「それは太平洋戦争あってこその話ですね」っていう、生い立ちから話してくれました。
それを聞くと、いまの前川さん像が分かるんです。前川さんの歌には、根っこにあるやさしさとか、(誰かの)悲しみにぴたっとくっつく感じとかが、出ていますよね。(授業を聞くと)「俺は分かっていたよ、前川さん」という不思議な感覚になります。
授業で聞き手役をやりながら、僕が泣いているっていうこともあります。つい最近だと石坂浩二さんの授業ですね。石坂さんも、本当のことなんか言いやしない、でも嘘はつかないという人。
その石坂さんがほぼ日の學校では僕が泣くような授業をしてくれているんですよ。
(※前川清さん、石坂浩二さんの授業は後日公開予定です)
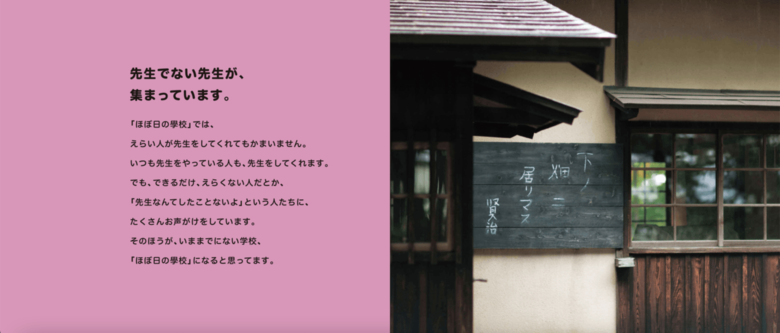

「その人の皮膚の表面に触れている」感覚
── 先生役はどういう基準で選んでいるのでしょう?
糸井さん:
強く生きてきた人、つらくても負けずに生きてきた人にお願いしています。そういう人が先生になって、真剣にしゃべってくれて「その人の皮膚の表面に触れているような気がする」っていう授業ができていると思います。
強いんだけど、ただ強いだけじゃなくて、弱さがある。その弱さについて、「もっと弱いこと言ってごらん」って言っても「いや、ないですよ」っていうようなタイプの人ばっかりです。
弱さとか、人の悪口で人を集めることもできるし、ヒステリックに泣き叫んでも人は集まるけど、それは相手の選択肢をとざす気がしてやりたくない。生徒がみずから気持ちよく参加する学校にしたいんです。
それから、よく言われる言い方にすると、「生まれてよかったな」って思わせられるような、そういう授業にしたい。
「一回も死にたいと思ったことなかったな」というのがいちばんいい人生だけど、死にたいと思ったことがあって、でも「あのとき死ななくてよかったな」っていうのはもっといい。
ほぼ日の學校は、そう感じられるものが全部入っていると思います。

(災害があるたびに現場に駆けつける)スーパーボランティアの尾畠春夫さんは、最初の先生の一人なんだけど、尾畠さんを選んだのは僕のお手柄ですね。あれでほぼ日の學校のイメージがものすごく自由になりました。
「型にはめない」から自由でおもしろい
── ほぼ日の學校の授業が、インタビューや講義形式など様々な形で行われているのはなぜですか?
糸井さん:
これは本人と相談しています。「糸井さんに聞いてほしい」と言う人の授業では、僕が聞き役をやります。誰もいないほうがやりやすいという人もいて、そうすると、ただのラジオ番組みたいになるけど、それはそれでいいんです。
── 糸井さんが先生役になる予定は?
糸井さん:
まだ撮ってないけど、やろうと思ってますよ。たとえば「僕がやってきたことは真似しかない」という話。みんなに「なーんだ、だったら俺にもできるんじゃない?」と思ってもらえるような授業をしたいです。
僕はコピーライターだから、コピーの話から始めようと思うんだけど、そうじゃないところの話もしようと思います。「なんとなく自分って普通かな」と思っている人や、「自分はまだまだだ」と思っている人が、授業を見て「この辺ならいけるかも」と思うかもしれない。

── おすすめの授業や楽しみ方を教えてください。
糸井さん:
どの授業もいいと思っていて、たとえ「面白くなさそうだな」と思った授業を見ても、「やっぱり面白くなかった、外れだよ」とはならないような気がするんですよね。
アプリの使い方でいうとイヤホンで聞くのがすごくおすすめ。間に雑音が入らないというのはものすごく助かります。
こういうおすすめの仕方がやっとできるようになった気がします。リリース前は自信がなかったんだけど、リリースして自分がお客になって客観的に体験してみて「内容はいいに決まってる」という余裕が出てきた。
真剣に聞くのもいいし、リラックスしながら聞くのもいい。聞き心地の良さから寝ちゃってもいいと思いますよ。
…
大人になると、学ぶ時間はすみっこに追いやられがちに。ですが、忙しい毎日を強く生きのびなければならない大人にこそ、糸井さんの言う「学び」が必要なのかもしれないと思いました。次回は、ほぼ日の學校づくりの裏側について聞きます。
PROFILE 糸井重里さん
株式会社ほぼ日代表取締役社長。コピーライター。「ほぼ日刊イトイ新聞」主宰。2016年糸井重里事務所を「株式会社 ほぼ日」に改称。2021年「ほぼ日の學校」をアプリで開校した。エッセイスト、作詞家としても幅広く活躍している。
取材・文/木村彩 写真/桜木奈央子