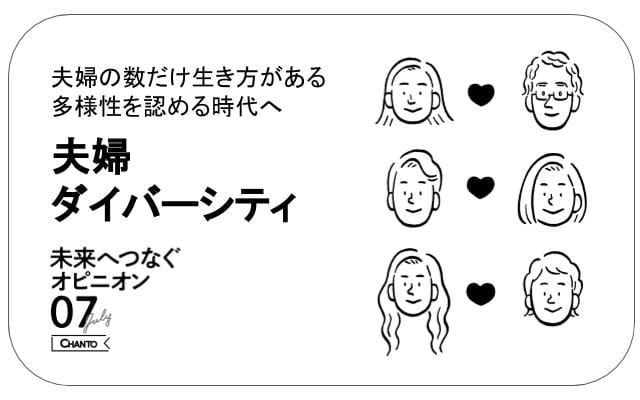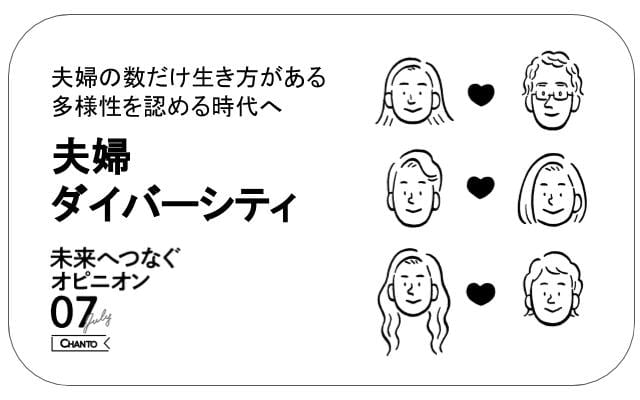
ここ数年、様々な場面で「多様性(ダイバーシティ)」という言葉を聞くようになりました。性別、国籍、年齢、職業、生き方……。人それぞれの人生や価値観を否定せず、認め合うことが求められる時代を迎えています。
夫婦の関係はどうでしょうか。男は仕事で女は家事という、ジェンダーによる古い役割分担が変わってきたように、「法的に婚姻関係を結んだ男女が一生を添い遂げる」という夫婦のあり方が、当たり前ではなくなる未来もそう遠くはないかもしれません。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、働き方を大幅に見直すことになった今、「夫婦のあり方」も見直してみると…?今の暮らし方、夫婦や家族の関係に心から納得できているでしょうか。自分の思いとのズレに気づいているのに見て見ぬふりをしているなら、少し立ち止まって考えてみてはどうでしょう。
今回は、まさしく「多様性」を感じさせる夫婦関係を築いている方々にお話を伺い、これからの「夫婦ダイバーシティ」について考えたいと思います。
まず最初に、社会学者の筒井淳也さんに、専門家の立場からみた「夫婦の多様化」について伺いました。
Profile 筒井淳也さん
専門は家族社会学、計量社会学、女性労働研究。1970年福岡県生まれ。一橋大学社会学部、同大学院社会学研究科、博士(社会学)。著書に『仕事と家族』(中公新書)、『結婚と家族のこれから』(光文社新書)、『社会学入門』(共著、有斐閣)など。
想像力が必要な時代の到来…「夫婦」という言葉に振り回されないで
——“夫婦の多様化”というと、事実婚や国際結婚が思い浮かびますが、専門家の立場から日本の現状をどう捉えていますか?
筒井さん:
事実婚は明らかな多様化のひとつで、日本でも増えてきています。かつては、籍が入れられない事情があるカップルの選択肢でしたが、最近は自ら選択する人もいますよね。女性の経済力が増したことで夫婦関係が対等になり、名字を変えたくない女性が増えたという背景もあります。
日本では「選択的夫婦別姓制度」が認められていないので、私の知り合いで、結婚の際にジャンケンで決めて妻の姓を名乗ることを決めたカップルもいます。彼らは仕事面でも収入面でも完全に対等な関係でした。お互いが自立していれば扶養関係にもならないわけで、生活への影響も少ないのでしょう。
国際結婚については、社会学的には「民族的な出自、あるいはその自認が違う人同士の結婚」ととらえます。以前は日本人男性が東南アジアの女性と結婚するケースが大半でしたが、近年は日本人女性と外国人男性という組み合わせが増えました。とはいえ、国内の異民族結婚の数自体はおそらく増えていません。
同性のカップルについては、自治体によってパートナーシップ制度を定めているところもありますが、同性婚が日本では法的に認められていないので、統計データがありません。同性法律婚が許容されたときに、それが増えていくかどうかはまだ未知数。なので「日本の夫婦が多様化しているか?」という質問に対しては、「少なくとも現状はしていない」と答えざるを得ません。
日本の社会でこれまで標準とされてきた家族の形を法律で変えることは、皆さんが思っている以上に難しい。ただ、世の中が「そういう多様性を許容しよう」という方向になってきているのは間違いないと思います。
——自分が“多様性”の当事者でなくても、今後、多様性のある人と関わることも増えてきそうです。無意識に相手を傷つけないためにも、意識すべきことはありますか?
筒井さん:
多様性の気づきにくい例としては、子どものいない夫婦が挙げられます。実は未婚・独身よりも数が少なく、マイノリティな層です。
近年は「結婚しているの?」と人に聞きづらい風潮はありますが、結婚している人に「お子さんはいくつくらい?」と聞いてしまう人は少なくありません。これは「夫婦=子どもがいることが標準」という考えによるもの。世の中にはさまざまなタイプのライフスタイルがあることを知って、想像力を働かせてほしいです。
「家族」という言葉には引力があります。多くの人が「パパが働いてママが家にいて、子どもがいる」という標準に想像力を限定させる。最近ではママが働くところまでは想像しやすくなりましたが、それ以外は頭から抜け落ちてしまいがち。それでは多様性のある社会とはいえません。
メディアが気軽に「ダイバーシティ」と言っても、口だけでは意味がない。同性婚や夫婦別姓を認めない、異民族結婚も少ない現状ですから、まだ根幹のところで“ダイバーシティのある社会”とは言えないのです。
共働き夫婦は、もはや“多様性”ではない
——多様性(ダイバーシティ)とは標準がないことだ、と理解しました。最近増えている共働き夫婦も「多様性」に含まれるのでしょうか?
筒井さん:
定義的には含まれません。女性の多くが専業主婦から共働きとなり、「古い標準」から「新しい標準」に移っていますが、これは多様性かというと、そうではありません。
世界的にみれば、フルタイムで働く共働き夫婦はすでに珍しくもなく、現代の標準です。ただし、以前は女性が働く場合は「自分の意思で働き続けたい」という声が多かったのですが、近年は「共働きでないと経済的に苦しい」という考え方にシフトしてきています。
その背景には、男性の雇用や働き方が不安定になっていることが挙げられます。「妻に家事をしてほしいけど、仕事も辞めてほしくない」と考える若い男性が増えていて、仕事の面で対等な関係を築きたいというのが、日本の夫婦のここ20年ほどの流れです。
——共働きの夫婦の場合、どうしても家事や育児の負担は妻のほうが大きいですよね。
筒井さん:
そう、日本は「驚くほど男性が家事をしない社会」です。共働きが増えているのに、それに見合う男性の家庭参加が少ない。育児休業にしても、男性の取得率は6%(※)程度。過去と比べれば増えてはいるのですが、とてもスローペースです。

というのも、企業のリーダーの考え方に変化がない限り、制度が大きく変わらないから。「自分はこうやって実績を上げてきた」という成功体験があるので、なかなか今までのやり方を変えられないんです。
一方、新しい考え方に理解のある人もいます。そういう人がリーダーに就くと、企業全体が一気に変わることも。政治家も含めて、社会全体のリーダーが保守的な考えを捨てて、本質的に変われないと難しい問題です。
女性が稼ぎ、男性が主夫——夫婦の形はもっと自由に選んでいい
——新型コロナウイルス感染症の影響で、働き方も見直されています。これらを受けて、未来の夫婦のあり方に、変化は生まれそうですか?
筒井さん:
リモートワークは、共働きの切り札だと20年以上言われ続けてきました。ライフワークバランスを実現するのに最も効果があると。でも、これまではまったく進まなかった。それがコロナ禍で半ば強制的に一気に進んだので、今後はリモートワークがより増えるでしょう。
実は、リモートワークしやすい職業に就いているのは男性のほうなんです。女性はパート労働が一番多く、その多くはデスクワークではありません。今後は男性が家でリモートワークをして、女性が外に仕事に出るという働き方も増えてくると思います。
現在の日本において、専業主夫の男性の数はここのところ10〜20万人で推移しています。この数が増えてもっと目立つようになればと思いますが、なかなか難しいですね。女性が家事・育児をしやすいように社会が最適化されてしまっているので、徐々に変えていくしかなさそうです。
——収入面で対等な夫婦でも、転勤や子育てを理由に女性が仕事を辞めるケースが多いです。どうしたら、本当の意味で対等な社会になるのでしょう?
筒井さん:
同じだけ稼いでいるのに不思議ですよね。いまだに「将来的に仕事を続けるのは男」という考えがあるので、常に女性のほうが補助的になります。女性が長期間働けるだろうと確信を持てる社会になることが、まずは大事です。
女性の離職率を減らすためには、無駄な転勤や出張をなくすとか、長時間労働はしないといった変革が求められるでしょう。これは、リモートワークの導入で大きく変わる可能性もあります。
男性の家事・育児が補助的な内容にとどまっているのも改善すべき課題ですね。男性が家事量を1増やしたら女性の家事量が1減るのかを調査したところ、ほとんど減らなかったという報告があります。少し手伝うくらいでは女性の負担感は変わらない。対等な夫婦になるには、男性が本気で取り組む必要があります。

また、賃金の発生しない労働も“仕事”と位置づけることで、社会的な価値観を変えていく必要もあります。たとえば、家事・育児・介護を一人で抱えている専業主婦がいたとして、今の日本では、その人は「仕事をしていない人」と扱われてしまうわけです。
ドイツでは、家で高齢者を介護している人に政府から現金給付が行われます。これにより、「お金がもらえるくらい大変な仕事をしているんだ」と人々の意識が変わってきた可能性があります。
多様化する社会をつくるためには、国の制度も大事ですが、各自の考え方を変えていくことも、間違いなく重要です。
——どんな夫婦や家族の形でも、その人らしい生き方を認め合うことこそが“多様性”の第一歩と言えるかもしれません。次回は、旧態然とした固定観念にとらわれず、妻がメインで働き、夫がメインで家庭を仕切るという独自のスタイルを貫く夫婦にお話を伺います。

< 特集TOPに戻る >
取材・文/大野麻里 イラスト/小幡彩貴
※出典:厚生労働省「平成30年度雇用均等基本調査」 https://www.mhlw.go.jp/