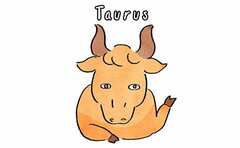松嶋尚美さんは、2021年9月、松嶋さんの妹さんが倒れたことで、妹さんが介護していた母を東京に呼び、同居介護をはじめます。しかしすべてが初めてのこと。介助の仕方など何もかもが探り探りだったといいます。(全4回中の2回)
階段、踊り場まで粘って!

── お母さんと同居をはじめるも、お母さんについてわからないことだらけだったそうですね。
松嶋さん:たとえば日常動作で言うと、着替えは腕を通すところを手伝うのかどうか。靴下は自分で履けるのか。冷蔵庫からモノを取り出すことはできるのか。食事は細かく刻んだ方がいいのか、そもそもどこまで食べられるのだろうかなど、全然わからなかったですね。
── 歩行は、室内では伝い歩きか歩行器を使用、外ではときどき車椅子を使っていたそうですが、予想外のこともあったそうですね。
松嶋さん:段差や階段があんなに大変だとは知りませんでした。母と同居を始めた当初、4階建てのマンションの3階に住んでいましたが、エレベーターがなかったんです。母が階段を昇るときは、母の右側と左側に私と夫がそれぞれついて、母の体を支えながら、母が足を一歩ずつ出していきます。でも、ゆっくりゆっくり進むので、3階まで昇るのに20分くらいかかってしまう。途中で足がガタガタ震え出すこともあって「踊り場まで粘って!」とも言えないし、どうにか母を支えている間に、子どもたちが慌てて部屋に戻って、踊り場に椅子を置いてくれたり、コップに水を入れてきてくれたりとてんやわんや。階段を降りるときはさらに大変でしたし、母が外に出るときはそれだけで1日の大仕事でした。
また、今までほとんど気にならなかったのですが、体が不自由な人にとって5ミリ程度の段差も転倒のリスクがあることを知りました。実際、母はトイレに行くたびに転んでいたので、途中から私がトイレまで連れて行くようになったんです。ただ、当時は薬のコントロールがうまくいっていなかったのか、トイレの回数がかなり頻回で。特に夜中のトイレの回数が多くてひと晩に4回呼ばれるときもあれば、1時間半起き、短いと前のトイレから20分後に呼ばれることもありました。私も常に寝不足だし、同時に家事や子どもの世話もしていたのでどんどん疲れがたまって…。見かねた夫が「朝4時から俺が(母の)面倒みるから、寝てもらっていいよ」と言ってくれて、時間で交代した時期もありました。