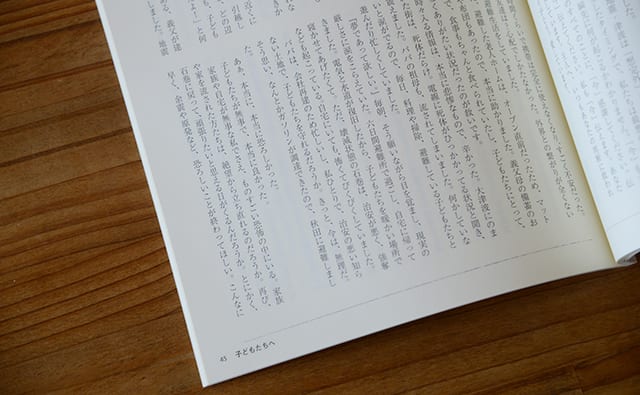「あのころ、私たちはただ、笑顔でいなきゃと思っていた。必死に笑っていました」
宮城県石巻市の親子を支える特定非営利活動法人「ベビースマイル石巻」の代表が発起人となり、被災地の母たちが言葉を寄せた文集があります。

そこには、震災後に子どもたちの前で気丈に振る舞ってきた母親たちの、ずっと胸にしまい込んできた声なき声が綴られていました。
文集は、こう名づけられました。
「子どもたちへ── ママたちがいま、伝えたいこと」
底のない悲しみも「子どもたちに言葉を残したかった」
「たくさんの命が犠牲になったあの日、私たちは“たまたま生き残った”と思っています。子どもを育てる母として、体験したことや気持ちを記録しておきたかったんです」
そう語るのは、この文集の発起人である荒木裕美さん(当時32歳)。
荒木さんが住む石巻は2011年3月11日、大きな津波の被害を受け、3200人以上の尊い命が失われました。
その日、荒木さんは街なかで子育てサークルのチラシを配ってまわっていました。大きな被害は免れたものの、自宅の一部が損壊。震災後はしばらくの間、その自宅で避難生活を余儀なくされたといいます。
亡き友人がしてくれたように「人を支えたい」
荒木さんは、震災でとても大切な友人Aさんを失いました。
当時、第2子妊娠8か月だった荒木さんとAさんは妊婦仲間でもあり、お互い励まし合う存在でした。
Aさんは体操サークル「すきすきすきんしっぷ」の代表として、親子体操をはじめ離乳食の会、小麦粉粘土遊びの場などを開催しながら母親たちをつなげていました。いつも母親たちを笑顔で励ましていたAさんに荒木さんは支えられ、救われたこともあったそうです。
3月11日、たまたま沿岸部へと出かけていたAさんは、そのまま戻っては来ませんでした。

信じたくない事実を知った荒木さんは、文集にこう綴っています。
数日がすぎ、携帯電話が通じると、「私」と「津波」を強烈に結びつける出来事が伝わってきました。友人・親戚・知人が犠牲になった知らせでした。行動を共にすることが多かった友人が犠牲になったことは、私も犠牲になるかもしれなかったという可能性を秘めていました。
「Aさんはいつも積極的に周りを巻き込んで活動していました。私も彼女のように、たくさんの人が集まり、支え合える場をつくりたい」。Aさんの想いを引き継いでいきたい…その覚悟が、今も石巻の親子のために走り続ける荒木さんの原動力になっています。

「Aさんのことは、最近になってやっと口にできるようになったんです」と、荒木さんはつぶやきました。「受け入れるのに、時間が必要だったんでしょうね」
あのころの私たちは必死に笑っていた
大切な友人の死を知らされ、一部損壊した自宅での避難生活を続けるなか、荒木さんはこれ以上ないほどの孤立感を味わいました。
「自分以外にも不安な思いをしている子育て中の人は多いはず。これ以上、困っている母たちをひとりにしたくない」。そんな思いで、母と子を支えるベビースマイル石巻を任意団体として立ち上げたのは、2か月後の2011年5月でした。

「ただ、最初はお母さんたちに電話をするのが怖かった。お子さんを亡くされたり、自宅が津波に流されたり…人によって被害がまったく違っていたので」
それでも、ホームページやメーリングリストで情報を届け、日々被害を受けた石巻の町を歩き回って見かけた建物をのぞいて空き室がないか確かめるなどして、必死で親子が集まる場所をつくっていきました。そこでは、おむつやミルクなどを配り、親子がリラックスした時間を過ごせるようにと温かな空間を守り続けました。

「あのころの私たちは、子どもを真ん中に置いて、いつも無理をしてでも笑っていました。なぜなら震災後、子どもたちが遊んだり、人が集まって楽しんだりすることに遠慮を感じるような時期が続いたから…。
子どもたちが何も気にせず、のびのび成長できることを大切にしたかった。底のない悲しみに押しつぶされないように、生まれる命や今ある命に目を向けたかった。お母さんたちになんとか希望をもってほしかったんです」
今、言葉にしないと後悔する
そう話す荒木さんが、「お母さんたちと文集を作りたい」と思いをまわりに伝え、プロジェクトが発足したのは震災から半年ほど経った10月でした。

「震災を経て、命を生み育てる母の視点は特別なものだという実感が強まりました。けれど、どこか強がって明るく振る舞う日々のなか、いつか『あの瞬間に感じた思い』が風化していくのではないか…そんな不安も感じていました。
『今、私がやらなければ』と思いました。聞くに聞けない話や、口に出すことができない思いもあったから。みんなの体験や気持ちを記録して、子どもたちに残すことがどうしても必要だと思ったんです」
母たちが綴った「声にならなかった声」
ベビースマイル石巻のメンバーを中心に参加した母親は30人以上にのぼりました。丁寧に言葉を紡いだ文集は、完成までに5か月を要しました。

綴られた言葉の多くから伝わってくるのは、母たちの「わが子を守りたい」という思いと、表面には決して出さなかった苦しみです。
終わらない揺れ、そして、あの津波警報のサイレン。用意していた非常袋をかかえ、ベビーカーに次女を乗せ、避難所へ行くことに。 お姉ちゃんが、「ちぃちぃが心配だよぉ!」と大好きなお人形の名前を呼ぶので、揺れ続ける中、自宅に走り、子どもたちの人形とオムツをつかみ、避難所である中学校へ。大雪の中、お姉ちゃんは、靴をびちょびちょにしながらも、頑張って歩いてくれました。あのときの濡れた靴下を思い出すと、今でも涙が出そうになる。中学校の体育館に避難する間も、鳴りやまない津波警報は、本当に恐ろしかった。(Bさん)
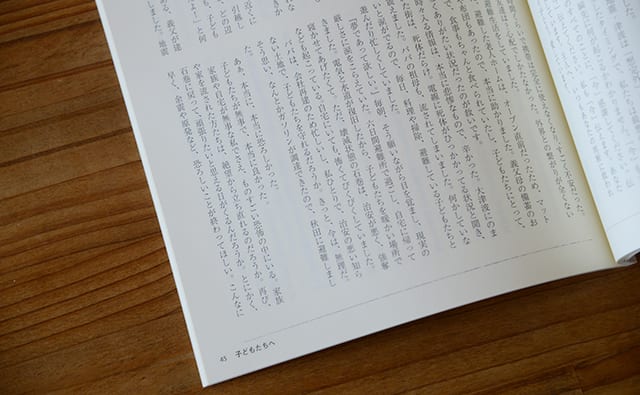
あの震災で私たちは津波の来る瞬間を見なかった。誰かの遺体を見ることもなかった。でも確かにあの瞬間、友人たちとその子どもたちが波にさらわれていった。自分の命よりも大切な命が目の前でさらわれようとしているのに、何も出来ないと分かった瞬間の母親の恐怖と絶望はどれ程のものだろう。(Cさん)

「子どもたちの前ではこらえていた思いを全部閉じ込めた1冊になった、と思いました。文集を読んで初めて知った思いもたくさんあって…。震災後、本音を言える場がなかったことに気づかされました」(荒木さん)
震災のことを自分から話すことはなかった
「文集を開くと、あのときの恐怖がよみがえりそうで。怖くて今まで開けませんでした」
当時、3歳の長女を育てながら2人目を妊娠していた伊東安奈さん(当時30歳)も文集に参加したひとりです。伊東さんも、荒木さんと同じくAさんの友人。Aさんは伊東さんにとってもかけがえのない存在でした。
「地震が起きた瞬間よりも、その後が怖かった。もし里帰り出産をしなかったら、私も石巻で命を落としていたかもしれない。神様ってなんなんだろう、と思いました。なんで?生かされた私はどうすればいいの?って…。でも、助かったのだから頑張って生きなければと、なんとか立っているような状態でした」

伊東さんは当時、石巻にいなかったことで、友人やまわりの人たちと同じ体験をしていない自分に引け目を感じていました。その気持ちは長く拭えなかったといいます。文集には、こんな言葉を寄せています。
この震災で私達家族は命も家(水はあがったが)も無事だった。その一方、友人の中には命を落としたり、家を失った人もいる。三・一一は私達への警鐘だと思う。今ある暮らし・家族は自然の力の前では、あっさりとなくなってしまうもの。だからこそ、今の普通の暮らしを大切に、日々に感謝しなくてはいけない。

文章を書いた当時の状況を振り返り、伊東さんはこう話します。
「自分の感情を揺さぶらないように、事実を淡々と書いていたように思います。普段はあんな書き方はしないんです。子どもたちに伝えたくて書いたつもりだったけれど、きちんと思いを込められたとは言えないかもしれない。震災のことを自分から話すことはなかったですから…」

伊東さんは、震災から2年後、夫の転勤で石巻を離れました。
「石巻にいられなかったことに後ろめたさもありました。でも、石巻では2人の子を授かり、まわりの人の温かさには本当に助けられました。私にとっては、大事な町です」
明日何があるかわからないから伝える
「外へ逃げたほうがいいですよ」
あの日、妊娠9か月だった小林真紀さん(当時31歳)は、自宅の3階で被災。ベランダに出たところ、外を通りかかった男の子からそう声をかけられました。
「地震直後は異様なくらい静かで…。でも、通りすがりの男の子のひと言で『やっぱり大変なことが起きたんだ』とハッと我に返りました。おなかの子のためにも孤立しちゃダメだって思ったんです」

すぐに母子手帳と産婦人科からもらっていた情報提供書をバッグに入れた小林さんは、不安を抱えながら避難所の小学校へ向かいました。文集では、避難所でのことをこう書いています。
私は体を冷やさないように、無理な姿勢を取り続けないようにと必死だった。外は火事で空が赤く染まっていた。ヘリコプターが何機も飛び、大きな音を立てていた。まるで戦争のよう。不気味だった。じっと、その様子を見ていた。被災地の私たちには何が起きているのか、どうなっているのか周りの状況がはっきりとわかるものではなかった。きっと大したことはない、そう思いたかった。それでもどうしても嫌なことが頭をよぎった。
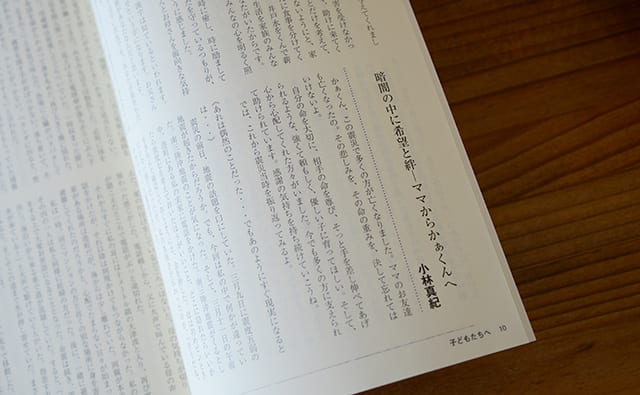
「両親と兄が気仙沼に住んでいます。当時は津波の情報が届いているかわからず、不安でたまらなくて。地震の直後に一度だけつながった電話で大津波が来ることを伝えることができて、両親たちが無事だったことは本当によかった。避難中に恩師とも電話で話せて、不安な気持ちを打ち明けられたことも、どれだけ支えになったか…」
その電話のやりとりのなかで、「あなたのおなかの中には赤ちゃんがいるのよ」と励まされ、目が覚めたといいます。

「私には守るべきものがある、と改めて自覚させられました。だから、辛く苦しい状況も耐えられたし、この状況を記録して子どもに震災の記憶を伝えなければという思いも湧きました。避難先で少しずつ書き留めたものが文集という形になったときはすごく嬉しかった」
今は、子どもと一緒にいられる幸せを噛み締める日々だと話す小林さん。
「『生まれてくれてありがとう。大好きだよ。会えて嬉しい』と毎日、伝えています。あの日から子どもにも親にも会えなくなった人がたくさんいたはず。自分の身にもいつ降りかかるかわからないと思うと、伝えずにはいられないんです」
11年経った今「人とつながり直せる嬉しさ」
荒木さんが被災した親子を支えるために「ベビースマイル石巻」を設立し、活動を始めてから今年で12年目になります。

当時、文集に参加した母親たちの中には家庭の事情で石巻を離れた人も多く「ベビースマイル石巻」を卒業した方々とは会う機会がなくなっていました。
ただ、今年に入って、荒木さんのもとに当時一緒に文集を作り上げた人たちから偶然連絡が届くようになったそう。
「つながり直しのような感覚でいます。11年経った今だからこそ、ということもあるのかもしれません」と語ります。

伊東さんも文集を作ってから10年ぶりに荒木さんに連絡をしたひとりでした。
「震災後は体調を崩すことがあったのですが、最近は落ち着いてきたので『自分ができることをしよう』と思えるようになって。何かできればと、荒木さんにメールしたんです。そういうタイミングが来たということかもしれませんね」
ふたりはコロナ禍で外出できず、閉塞感を抱く母親に向けてオンラインでイベントを開くことにします。今回の取材当日は、その準備の真っ最中でした。
「文集を一緒に作った人たちに声をかけているんですよ」と荒木さんは笑顔で話します。

「文集を作った10年前は、子どもがまだ小さかったし、とにかく精一杯でした。大人同士の会話もゆっくりできなかったと思います。今回、こんなふうに再び縁がつながって、新しい企画を一緒に考えられることが、とにかく嬉しいし面白いんです」
一生開けないと思っていた文集 泣きながら読んだ
伊東さんは、荒木さんに連絡をとったことをきっかけに、初めて文集を開きました。
「一生開けないんじゃないかと思っていました。でもやっと、自分以外の方の文章も読めたんです。どうしても泣いてしまうけれど」
そんな皆の声を聞くたび、荒木さんは「やっと、これまでを振り返る時期にきたのかな」と感じています。

ようやく苦しい経験を受け止め力に
「苦しい体験を受け止めて、力に変えていくには、時間がかかりますよね。文集を作るときには、私を含めて『被害が小さい自分に書く資格があるのか』と迷った方もいましたが、あの日思ったことを言葉にしたかった。
『こんなに大変だったんだ』と初めて自分が置かれた状況を理解した方も多かったし、苦しい作業だったと思います。でも、あのときにみんなで書いたから、自分たちの気持ちを風化させないまま、子どもたちにも読んでもらえるものになったと思っています。
『書いてよかった』とみんなが思ってくれるとありがたいですね」
震災後のあのとき、母親たちが綴った文集は石巻市内の書店「金港堂」の棚に今も並んでいます。助産師さんや防災に関心を持つ方などを中心に、少しずつ広がっているそうです。
取材・文/高梨真紀 風景撮影/辺見清二 文集イメージ撮影/徳増純一郎 画像提供/ベビースマイル石巻
※この記事は、CHANTO WEBによるLINE NEWS向け「東日本大震災特集」です。