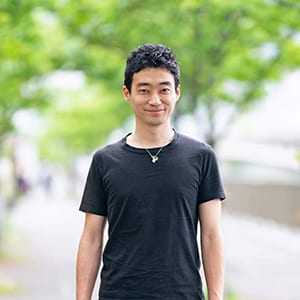2004年に3人の邦人がイラクで拘束された「イラク人質事件」。拘束されたうちの1人、今井紀明さんは当時18歳でした。
帰国後「自己責任」という言葉のもと、社会から猛烈なバッシングを受け、対人恐怖症に陥った今井さん。現在はそんな過去の経験から、10代の若者を支援するNPO法人「D×P」(ディーピー)を立ち上げ、代表として忙しい日々を送っています。
私生活では去年の春にパートナーと同居を始め、6歳と8歳の女の子のステップファーザーになりました。前回は、ステップファーザーとしての葛藤や、不安、ステップファーザーを巡る制度の不備などを伺いました。今回は、子育てを通じて感じた社会の課題、仕事に与えた影響などを伺います。

「男性の家庭進出」は必須 子育てで気づいた社会の課題
── 娘さんたちと同居を始めた20年は、ちょうどコロナが拡がった時期ですね。
今井:
僕も在宅ワークを始めた時期で、バランスの取り方には悩みました。事業の面でも、コロナ禍の影響で大きな財団からの寄付が急に打ち切りになったり、厳しい経営判断を迫られている時期でした。
仕事をしているときは、仕事にしっかり集中したい。そういう時に子どもが甘えてくると、どうしてもイライラしてしまうことがあって…。
僕の場合、子どもたちとのんびり関わる時間を持つために、まず土日には仕事をしないと決めました。平日の仕事時間も減らし、スタッフに任せることも増えました。
パートナーとも、役割や分担を都度話し合いながら見直し、少しずつバランスが取れるようになってきたと思います。
── スタッフとの関わり方にも変化はありましたか?
今井:
「D×P」には週4勤務で正社員のスタッフもいれば、学校教員でありながら副業として働いてるスタッフもいます。もともと職場の多様性を大切に考えてきたけれど、子育てが始まって、ますますその気持ちが強くなりました。多様な働き方を認め、職場を可能性のある場所にしたい。
あとは、日々の業務の中でも、社員に対して、より柔軟な対応ができるようになりました。
前までは「子どもが熱を出したのでお迎えに…」という話があると、「了解!」と言いながら「仕方ないけれど、この部分についてはこなしてほしかったなぁ」なんて思っていたんです。
でも今は「了解、すぐ行って!」と。「そりゃ子ども優先やろ」と感覚的に理解できるようになりました。

── 子育ての経験は組織としての働き方にも大きな影響を与えたんですね。
今井:
そうですね。子育っててこんなに大変なのかと、身をもって理解したのが大きかった。当たり前のことなんですが、「子どもがいるとこんなに部屋って散らかるんだ…」とか、「行政手続きってこんなに効率悪いのか…」とか、経験しなければわからないことがたくさんありました。
母親が仕事もこなしながら、これだけ多くの子育てタスクを1人で背負うのは絶対に無理だし、身体がもたない。
今は実感をもって「社会も政治も企業も、男性の家庭進出を積極的に促すべきだ」と言えるようになりました。「頼る先」がどんどん減っている現代においては、男性が家庭進出しない限り、女性の社会進出もありえない。これは僕自身が家事・育児を経験しなければわからないことでした。
男性も女性も、性別による「らしさ」に縛られない社会へ
── 他にも目が向くようになった社会の課題はありますか?
今井:
娘ができたことで「ジェンダーギャップ」についても目が向くようになりました。娘たちが大人になった時に、性差別を受けたり、女性の選択肢が狭い社会を生きて欲しくない。
コロナ禍で打撃を受けた非正規雇用者は多いですが、働く男性のうち非正規雇用の割合は16.8%に対して、女性は48.5%。影響を受けた女性は多かったと思います。
ふと周囲を見渡してみれば、衆議院の女性比率は10%と先進国の中で最低だし、メディアの女性役員の比率も2〜3%。
世界経済フォーラムが発表した「ジェンダーギャップ指数」も、
1980年代には80位程度だった、それが今は、120位。
世界から取り残されているな、と感じます。
── 今井さん自身が何か取り組んでいることはありますか?
今井:
男性ばかりのセッションや、組織のボードメンバーを誰にするかなどの相談を受けて、男性ばかりがあがってきている時に「ジェンダーバランス悪いので、僕じゃなくて他の方いれましょう」と提案しています。
そういう意識づけから発言の多様性とかも変わるかもと
思っていて。自分にできること、少しずつやっています。
── 娘さんたちが住みやすい社会を残すために具体的に動き出しているんですね。
今井:
こうした取り組みは、なにも女性のためだけじゃないと僕は思っているんです。
男だって「男らしさ」に縛られている。僕たちミレニアル世代(20代〜30代)は、まだまだそういう価値観が根強く残っていますよね。「男は酒を飲み、深夜まで働くもんだ!」とか。
「男らしさ」というバイアスがかかると、解像度が落ちて、本当の自分が見えづらくなる。本当はもっと中性的な部分があるかもしれないし、家庭のことが得意な男性だっているはずなんです。
性別による「らしさ」に縛られて自分らしい生き方ができない社会は、女性にとっても、男性にとっても害だな、と思う。僕らの世代がジェンダーについて学びなおすことは、絶対に必要だと思っています。

今井紀明さんと娘さん(6歳と8歳)
すべての若者に伝えたい「未来に希望を持って生きて」
── 最後に「D×P」の活動で得た経験が、どのように子育てに生かされたかを教えてください。これまで関わってきた学生たちの数は何人くらいいたのでしょうか?
今井:
7,000人くらいになると思います。
── 7,000人の若者と関わってきた、その経験が、娘さんたちを育てる上で生かされていると思いますか?
今井:
僕たちが若者と向き合う時に大切にしていることは、「否定せずに関わる」「様々な年齢やバックグラウンドの人から、学ぶ」ということです。
娘たちと突然の同居生活が始まって苦労したこともあったけれど、特に「否定せずに関わる」というスタンスを持っていてよかった、と思っています。家で一緒に暮らしていると難しいこともあるんですけど(苦笑)。でもこのスタンスがあったから、踏ん張ってこれた。
あとは活動を続けてきたおかげで、地域に娘たちを見守ってくれる知り合いがたくさんいます。うちにもいろいろな人が訪ねてきてくれます。多くの人に見守られながら子育てできているのはありがたいですね。
まだ道半ばではあるけれど、娘たちには、安心できる居場所を提供したい。そして、これは全ての若者への僕のメッセージですが、ぜひ、未来に希望を持って生きて欲しいと願っています。
…
日々の「暮らしの中で感じる課題」と「社会の課題」とを結びつけ、持ち前の行動力で現状を変えていくことができる今井さん。
「10代で社会から否定された」という経験から、「D×P」を立ち上げ、現在はコロナ禍で困窮する若者の支援に奔走していますが、「ステップファーザー」という新たな立場から社会を見つめる今井さんの言葉を聞いていると、「D×P」の活動は今後また新たな展開を見せるのかもしれない──。そんな「未来」を感じさせる取材でした。
PROFILE 今井紀明さん
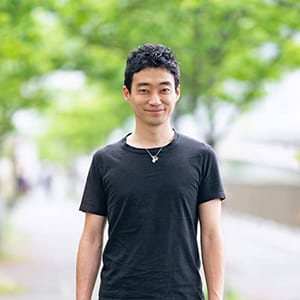
取材・文/谷岡碧