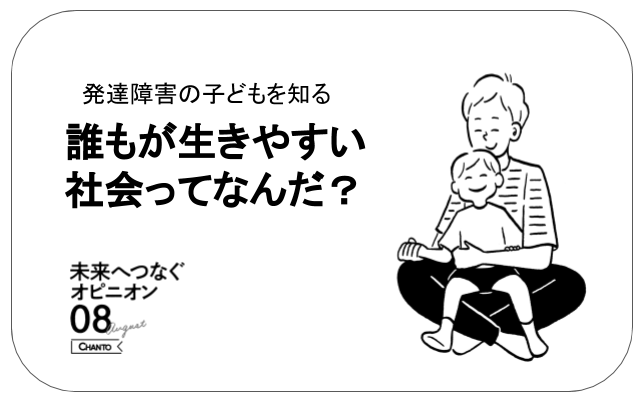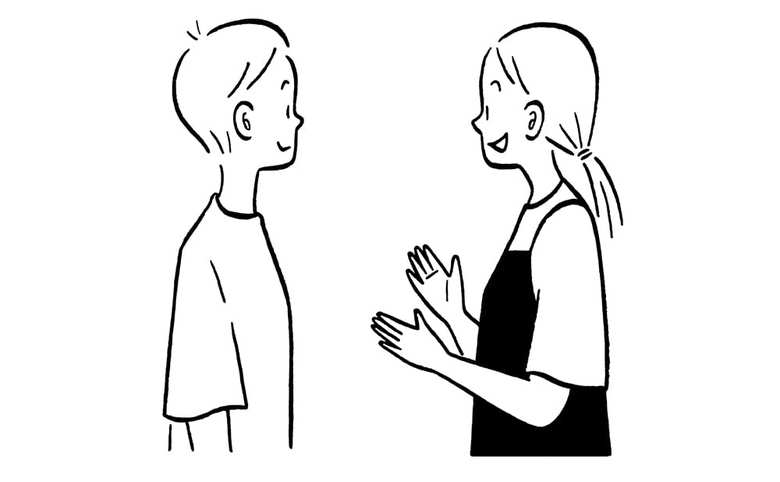発達障害の子育て、父親の参加率は?
——先生は約20年、発達障害の子どもの診察に携わってきたそうですが、父親の参加率は変わりましたか?
塩川さん:
まだまだ圧倒的に母子だけの受診が多数派ですが、最近では両親揃って受診や療育に参加する家庭も少しずつですが増えてはきているように感じます。
ただ、父親の考え方や思い込みが足を引っ張るケース、子どもによくない影響を与えているケースがあることを少々懸念しています。
せっかく医療機関を受診してわが子が発達障害と診断されても、「俺もそうだったから治る」「療育なんてやめろ」と反対する父親が意外と多い。現実を直視できない、あるいは受け入れきれずに、目を背けてしまうというケースです。
祖父母も含め、父親も子どもにとってはもっとも身近でもっとも力強いサポーターですので、これらの人たちにも積極的に理解を求め巻き込んでいくことが大切です。家族の理解を求めるためには、やはり情報をきちんと共有することが必要でしょう。
——否定的な家族を巻き込んでいくにはどうすればいいでしょう?
塩川さん:
ご自分でうまく説明できない場合は「健診を受けたら、お医者さんがこう言っていた。聞きたいことがあれば先生に自分で聞いて」と診察現場に引っ張り出すのがいいでしょう。あるいは「こういうアドバイスをもらったから家でも一緒にやろう、私はこれをするからあなたはこれをやってね」というように巻き込んでしまうことです。
サポーターは多いに越したことはありません。支援は連携してすること、連携は情報共有と役割分担することが基本です。
小学校に入る前に考えておきたいこと

——小学校入学前に考えておいたほうがいいことはありますか。
塩川さん:
小学校入学にあたって、通常学級と特別支援学級、どちらを選択すべきか悩まれる保護者も多いでしょう。グレーゾーンとされるお子さんの保護者はなおさら悩ましいかもしれません。
学校の選択をする場合、親としてまずは、その学校・教室を選んだ場合、子どもがどのように感じどのような体験をすることになるか、イメージを持つことが大切です。常に子どもの視点にたって考えていただきたいと思います。
たとえば、学習の遅れについて心配される方もおられますが、通常級に入ってもクラスメートと会話ができず、いじめの対象になってしまうこともまれではありません。そういう環境に無理やり放り込むことは発達面や情緒面によくない影響を与える場合もあります。
もちろん担任の先生が通常級での支援の経験が十分にある場合、クラスメートの理解や受け入れがある場合であればその心配はありませんが、そのような例は多くはないと思います。
著名な先生がおっしゃっていましたが、「グレーというのは白ではなくて薄い黒」という意味で、つまりその子がグレーならそれは支援が必要な子どもであるということです。そういう意味では、支援級のほうが学習や行動面・情緒面に対する支援が受けやすいですし、特別支援学校ではさらに手厚い支援が受けられます。
支援級に抵抗感を持つ保護者もいるかもしれませんが、支援級のほうが子どもの困り感が減るのは確かです。また、通常学級に在籍しながら、週に何回か通級する、という方法もあります。
わが子の場合はどういう環境であれば学校生活を楽しめそうか、可能性が広がりそうか、ということを、就学前相談などでじっくり話し合ってみてください。子どもの視点にたって、子どもの特性によりマッチした就学環境を考えてください。
——将来の職業選択などにおいては、どんなビジョンを抱いておけばよいでしょうか。
塩川さん:
発達障害だからこれがいい、という進路はありません。本人の特性に合わせて得意分野を生かすことを目指すのがやはりいいと思います。各自治体では発達障害者支援センターが整備されています。特別支援学校でも、就労についての手厚いサポートをしてくれるはずです。
実は、社会に出てから最も当人が苦労してしまうのは、「発達障害であることに気づかないまま有名大学を卒業して就職する」ケースなんですね。就労先に配慮を求めても、なかなか叶えられませんし、就労先の理解を得ることもかなりの困難を伴い、それを乗り越えるための労力が必要になりますから。
そういう意味でも、発達特性の偏りについては人生の早い段階で気づけるほうがいい。
また、発達障害の子に特別な才能を期待する保護者もいますが、それ以上に重要なのは「情緒の安定」です。自分の特性を受け入れているか、周囲に受け止めてくれる人はいるか、安心できる居場所はあるか。そうすることで得られる情緒の安定が、社会適応を最も左右します。
——わが子だけでなく、身近に発達障害の子どもがいる場合、大人としてできることはありますか。
塩川さん:
ADHDなどのラベルでその子を括ろうとせず、その子自身・その子の内面的な部分も含めた本当の姿を見てあげましょう。「この子はこんなふうに感じているのかな?もしかしてこんなことに困っているんじゃないかな?」と想像して、その仮説に基づいてフォローできることがあればしてあげる、できそうなことが特にないのなら温かく見守ってあげましょう。
名札貼り(病名診断)は、専門家の仕事。周囲の人は、原因や犯人探しをせず、あるがままのその子自身を受け入れてあげてください。それから、自分ができる範囲でサポートしてあげましょう。その子ども・人にとって必要なサポートがいつでもどこでも空気のように手に入る社会になれば、「発達障害」という概念そのものがなくなる未来もあるかもしれません。
… 「特性に偏りのある人が生きやすい社会は、誰にとっても生きやすい社会」。塩川先生のこの言葉は、発達支援の目指す方向を明確に示しているように感じます。次回は、アンケート調査を通じてわかった発達障害をめぐる認識のズレについて、リアルな声と悩みを伝えていきます。
PROFILE 塩川宏郷さん

実践女子大学 生活科学部教授。1962年、福島県生まれ。87年、自治医科大学卒。福島県内のへきち医療に従事後、自治医科大学附属病院小児科、とちぎ子ども医療センター心の診療科、東ティモール大使館、東京少年鑑別所、筑波大学を経て2018年から現職。専門領域は発達行動小児科学、小児精神医学。『もしかして発達障害? 子どものサインに気づく本』の監修を務める。

文/阿部 花恵 イラスト/小幡彩貴