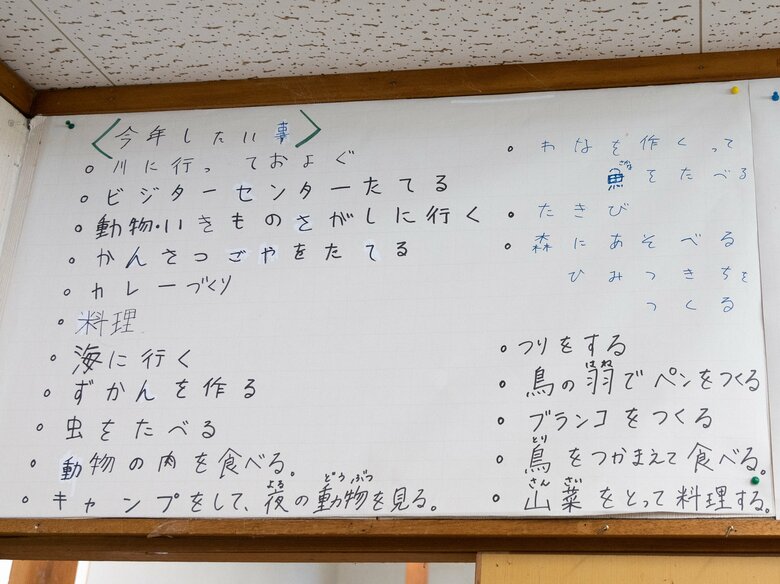就職希望者があとをたたない和歌山県のある学校。その秘密はどこにあるのか。お金で測れない教える大人側の学びがあるそう。夫婦で転任した先生が体験した学校での日々とは。

「募集していませんか?」と教師からの応募が絶えない学校
近年は全国的に教員不足が深刻化しています。文部科学省の調査によると、令和3年度(5月1日時点)の教師不足は小学校で979人、中学校で722人にのぼりました。
ところが、きのくに子どもの村学園には募集をかけなくても、「働きたい」と多くの希望者が集まります。なかには「移住してでも教員になりたい」と、夫婦で志願する人も。
「教員同士の論争や、いさかいがあると学校経営はうまくいかない」と話すのは学校長の堀真一郎さん。年齢や経歴に関わらず教職員の基本給を一律にする理由をこう話してくれました。
「本校のモデルになった、イギリスの『サマーヒル・スクール』創設者ニイルの奥さまから『自由学校を経営する秘けつは給料に差をつけないこと』と、アドバイスを受けました。基本給が一律なら争いや嫉妬、上下関係が生まれず、子どもの幸せを考える大人だけが集まりますから。ふつう、モノの値段は『どれだけ役立つか』で決まるじゃないですか。でも学校やったら、『どれだけ子どもの力になれるか』です。経験がない新米の教員でも、子どもにとってはありがたい存在かもしれない。子どもとのフィーリングに年齢も経歴も関係ないでしょう」

基本給に差をつけないかわりに、扶養手当は公立学校の約3倍の額を支給しているそう。夫婦で働く教職員は学園全体で15組を超え、自分の子どもや孫を入学させる人も少なくありません。
この学園では、教職員113人のうち20名が卒業生、約35人が保護者と元保護者、さらに大学の講義で知ったり、本学園についての卒論を書いたりして大学卒業と同時に参加してきた人が28名です。そのほか公立学校で勤務していた人やNPOからの転職などバックグラウンドはさまざまですが、いずれも学園の教育理念に賛同した人たちが集っています。
「子どもの幸せについて葛藤していた」教員夫婦が移住
きのくに子どもの村学園の特徴のひとつは、「先生」がいないこと。大人たちは、子どもから「堀さん」「さとちゃん」「まるちゃん」などのニックネームで呼ばれます。心理的な上下関係をつくらず、距離の近い関係性を築くためのアイデアで、同校のモデルとなった「サマーヒル・スクール」でも実践されています。
公立学校に25年以上勤務していた「さとちゃん」こと佐藤由里さんは、同じく教員の夫「よっちゃん」と、2022年4月からきのくに子どもの村学園で働き始めました。他県からの移住で、この学校に来て約1年になります。佐藤さんがこの学園を知ったきっかけは10年前、息子がもらした「学校が合わない」というひと言でした。
「子どもに合う学校を探しているとき、この学校のことを知りました。息子はタイミングが合わず入学できませんでしたが、子どもの幸せをいちばんに考える校風は私にとって理想でした。公立学校で働いているときは、ずっと葛藤していたんです。大人の価値観に子どもを従わせて、子どもは幸せなのか。

たとえば、コロナ禍によるIT教育の前倒し。パソコン画面から得る知識や技術を覚えるよりも、人と交流し、体を使って体験する楽しさが子どもの幸せ、生きる力につながるんじゃないかなって」
「自分に正直に生きたい」という思いが強くなったときに、佐藤さんはきのくにこどもの村学園を見学するチャンスに恵まれました。愛があふれている現場に感動し、「子どもと自分の幸せのためにここで働きたい」と決意。同じく関心を持っていた夫とともに移住し、この学園の一員となりました。
「“俺”って言い方は…」と諭すと子どもが返した見事なひと言
佐藤先生は働き始めた当初のことを、「公立学校との違いに戸惑った」と振り返ります。
「ここでは子どもに『しなさい』と言うことはありません。『話は前を向いて黙って聞いて』『整列して移動するんだよ』などと、大人の決めたルールを守らせることもありません。何事も『こんなときどうしたらいいんだろうね』『あなたはどうしたい?』と子どもに問いかけます。たとえば入学式の代わりに開く“入学を祝う会”では、委員の子どもが全校生の意見を聞きながら企画します」
“入学を祝う会”は一般的な入学式とは異なり、子どもが風船を飛ばしたり、くす玉を作って割ったり、お祭りのようなイベントになるそうです。子どもたちはジュースで乾杯し、豪華なおやつを食べてお祝いします。みんなが楽しみにしている恒例の宝くじでは、子どもたちがデザインしたオリジナルパーカーや、自分たちで飼育している鶏の産みたて卵などが景品に並びます。

「子どもには自分で考えて決める力がある、と信じている学校なんです。大人は必要以上に手も口も出さず、行き詰まったときに一緒に考えたり、影からサポートしたりします。赴任した当初は何をしたらいいのかわからなかったですけど(笑)」
公立学校とは何もかも違う環境で、佐藤さんは「子どもたちから教えてもらうことも多い」と話します。
「ある子が、『俺だって』と話し始めたので、『“俺だって”だと自慢に聞こえちゃうから、“俺も”にしたら?』と言ったんです。そうしたら、離れたところで本を読んでいた4年生の女の子が『別に自慢したっていいんじゃない?』と。そっか、その通りだって思いました。いつの間にか“これが正しい”、“これがあなたたちのため”と凝り固まった価値観になっていたなと、小さな会話から気づくことが多いんです」
この前おもしろいことがあって、とうれしそうに笑いながら続けます。
「きのくにに慣れて肩の力が抜けてきたころだったかな。詳細は忘れましたが子どもの質問にちょっとブラックユーモアを効かせて返事をしたら、子どもから『さとちゃんも腹黒くなったな。つきあいやすくなってきたよ』と言われて(笑)。“きのくにの大人”として認められたようでうれしかったです。私はそれまで、教師という立場を意識するあまり、子どもにまともな受け答えしかできませんでした。子どもと大人は対等、決して大人が上の立場ではないと実感したできごとでしたね」
取材・文・撮影/白石果林 画像提供/きのくに子どもの村学園