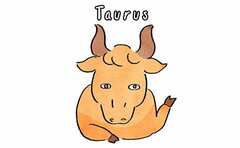8年続くニトリのCM出演や、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の演技で注目を集める俳優・清水伸さん。多数の作品に出演し、劇団ふくふくやでは副座長を務めています。今、俳優業に脂の乗る清水さんの根底には、井筒和幸監督率いる「井筒組」のイズムがあるそう。一緒に働く人との「共通言語を持つ」という仕事論は、私たちにも通じるものがありそうです(全4回中の4回)。
「芝居という形のないもの」をつくるうえで重要なこと
── 多くの作品に出演していますが、俳優人生に影響を与えた出会いは何ですか?
清水さん:
いちばん大きいのは井筒監督、というより「井筒組」ですね。
井筒監督は名監督を育てる監督です。名だたる監督が「井筒組」で助監督をやっていました。
「井筒組」の現場はひと月ほどかけてリハーサルをしますが、その現場に井筒監督は現れません。助監督が俳優を「井筒組」のトーンに合うキャラクターに1か月かけて仕上げていくというのがリハーサル期間にやることです。つまり井筒監督のイズムが分かっていないと務まらない。
そういう方たちと一緒に井筒監督に見せるためにキャラクターをつくっていく、そこで得た共通言語が今でも役に立っています。
「井筒組」から巣立ち、名監督になった方たちと「あのときの『井筒組』の感じで」と、ツーといえばカーと話せる人と仕事ができるのは、芝居という形のないものをつくるうえではとても重要です。
勝手知ったる人たちが揃って一緒にひとつの作品を作る、それが「組」という形の良いところ。
怒られた記憶ばかりだけど、あのときの経験が生きていると感じることはよくあります。今、こうやって役者の仕事を続けていられるのは、あの頃築いた礎のおかげだと思っています。

── 清水さんの根底に流れているのは「井筒組」のイズムということなのですね。
清水さん:
大きいと思います。
『地獄の黙示録』も観てない奴が、俳優すんじゃねえ!
── 怒られた記憶ばかりとのことですが、大切にしている言葉のようなものはありますか?
清水さん:
具体的な言葉ではないですが、学んだことのなかに「井筒監督の好きな映画を観る」というのがあります。
分かりやすいところで言うと『ゴッドファーザー』。井筒組から巣立った名監督のひとり、武正晴監督だと『地獄の黙示録』。
カメラワーク、セリフの言い回し、表情の見せ方など、何かにつけて引き合いに出してくるので、作品を観ていないと何を話しているのか分からない。
松尾諭さん原作の『拾われた男』というドラマで「『地獄の黙示録』も観てないやつが、俳優すんじゃねえ!」といったセリフが登場します。
── ありましたね。
清水さん:
あの作品は、武監督の盟友である足立紳さんが手がけた脚本で、松尾さんの原作にも、当時の助監督だった武さんに言われたとの記載があるそうです。
最近だとコンプライアンス的なこともあるだろうけれど、僕らの時代は映画人たちと共通言語を持つことはモノづくりをするうえでとても大切なことだったので、井筒監督の好きな作品は片っ端から観て、ディスカッションしました。
1を聞くと10教えてくれる方なので、本当に楽しかったし勉強になりました。
影響を受けた素敵な言葉も数えきれないくらいあったはずだけど、浮かんでくるのはたくさん話をした光景ですね。
これからは誰かの笑顔のために演じる
── 現在50歳。俳優として、清水さん本人として目指すことを教えてください。
清水さん:
何かを悟ったわけでもないけれど、目指すことは特にないというのが正直なところです。
ただ、いつも自分のなかで言い聞かせているのは、人を笑顔にして幸せにするお芝居を届けられるように、ということ。それがないと、自分がやっている意味がないと思っています。
僕の劇団の公演は基本的には東京です。でも、関西や九州など地方から足を運んでくださり、「清水さんにお会いしたくて」とか「ニトリのCMを見ると元気が出て前向きになれます」とか「清水さんの顔を見て、思いきって来てよかったです」と声をかけてくださいます。
誰かが少しでも笑顔になって、幸せになってくれる、そんな演技をお届けしたいと思うと同時に、それは僕がやっていかなきゃいけないことだと考えるようになりました。

── 自分がどうなりたいかではなく、「誰かを笑顔のために」って素敵ですね。
清水さん:
もうちょっと若かったら、連続ドラマの主演をやりたいですと答えるのかもしれないけれど、もうこの歳ですから(笑)。
── お話もとてもおもしろくて、インタビュー中は終始笑顔にさせていただきました。ありがとうございます。
清水さん:
よかったです!
PROFILE 清水 伸さん
俳優。1972年生まれ、新潟県出身。2022年の出演作は大河ドラマ『鎌倉殿の13人』やドラマ『恋愛ディソナンス』、『ユーチューバーに娘はやらん』など。2015年よりニトリのCMに出演。劇団ふくふくやにて副座長を務めている。
取材・文/タナカシノブ